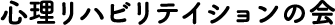【リレーエッセイ(トレーナー8)】
和歌山県立たちばな支援学校 岡本宗宜
和歌山県の知肢併置の特別支援学校で教員をしております岡本宗宜と申します。大阪大谷大学の向先生からのリレーのバトンを受け取りました。私にバトンを繋げてくださったのは、他の皆さんとは少し違った視点からの話を、という意味だと解釈し、自分のこれまでの経験を綴らせて頂きます。
私は高校卒業後、福祉現場で働きながら大学の通信課程を卒業し、和歌山県の教員となりました。講師として養護学校(当時)で勤務後、採用されたのは盲学校でした。盲学校には視覚障害だけでなく様々な障害が重複した児童生徒もいましたが、当時の養護・訓練は点字や白杖歩行等の指導が主で、重度の肢体不自由や知的障害のある児童生徒に対応したものではありませんでした。必死で様々な研修に行きましたが、納得できるものはなく、ようやく辿り着いた大阪での動作法研修会で、これまで感じられなかった魅力を感じました。スタッフの先生に和歌山の月例会を紹介頂き、飛び込んで動作法を学ぶ中で、子どもとの「やりとり」を体験し、自分が探していたものはこれだと確信しました。そして実際に学校で取り組むと、児童生徒にも変化が見られ、動作法の魅力にさらに惹かれていきました。
和歌山県では動作法は盛んではなく、月例会もキャンプも小さなものです。県内に動作法に取り組む大学機関がないことが大きな要因ですが、それでも保護者の皆さんは熱心で、やすらぎ荘や大阪のなにわキャンプにも参加されていました。その熱意により、大阪から小田浩伸先生をはじめたくさんのSVの先生方が和歌山に指導に来てくださいました。成瀬先生に来て頂き、公開研修会を開催できたのも、保護者と大阪の先生方の熱意によるものでした。そのようなたくさんの支えの中、私たちは育てて頂きました。
その後、私はなにわキャンプにも参加するようになりましたが、その勢いや熱量、一体感は衝撃的でした。トレーナー、トレーニー、SV、保護者・・・みんなが同じ方向を向いて進んでいく。こんな世界があったのかと、感動を覚えました。しかし和歌山に戻ると現実は厳しく、トレーナーは増えません。そのため、少ないスタッフがいくつも役割を担う形で、なにわを目指しつつ、和歌山オリジナルの形を作っていきました。大阪の先生に支えられながらも、自分たちでキャンプが運営できた時、これまでとはまた違った一体感や充実感を得ることができました。動作法で味わう「やりとり」の実感と、参加者全員で作る一体感や充実感が、他にはない心理リハビリテイションの魅力であり、その魅力のおかげで、県内にも少しずつ仲間が増えていきました。
現在も、学校現場で日々子どもたちと関わっていますが、動作法で学んできたことが、関わり方の基礎となっています。「学校現場ではなかなか動作法を活用できない」とおっしゃる方もおられます。確かに、「どうぞ動作法をしてください」という環境はあまりありませんが、私は動作法の考え方や技術を活かす場面はたくさんあると感じています。実際、私は自立活動の時間のほか、集団授業の場面、朝の迎えの場面、教室への移動、トイレ指導、食事場面、休憩時間、他のクラスの子どもと関わる場面、帰りの場面など、その瞬間瞬間に動作法で学んだことを大切にして関わっています。そして保護者対応や教員同士、他機関との話し合いでは、研修やミーティングでの経験が活かされています。明確に動作法を行う場面がなかったとしても、主体的に動作法を活かす場面を見つけ、作っていくことが必要であり、それが学校現場で有効であると考えています。
長々と書いてしまいましたが、このような機会を頂き、ありがとうございました。そしてこれまで私に心理リハビリテイションの素敵な、貴重な経験をさせてくださった大阪、和歌山の関係者の皆さん、ご指導くださいました様々な地域の先生方に、心から感謝申し上げます。コロナ禍以降、キャンプや月例会運営は、さらに苦戦を強いられています。しかし少しでも動作法の魅力を伝え、関わって頂いた皆さんに恩返しができるよう、私も微力ながら努力していきたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願い致します。